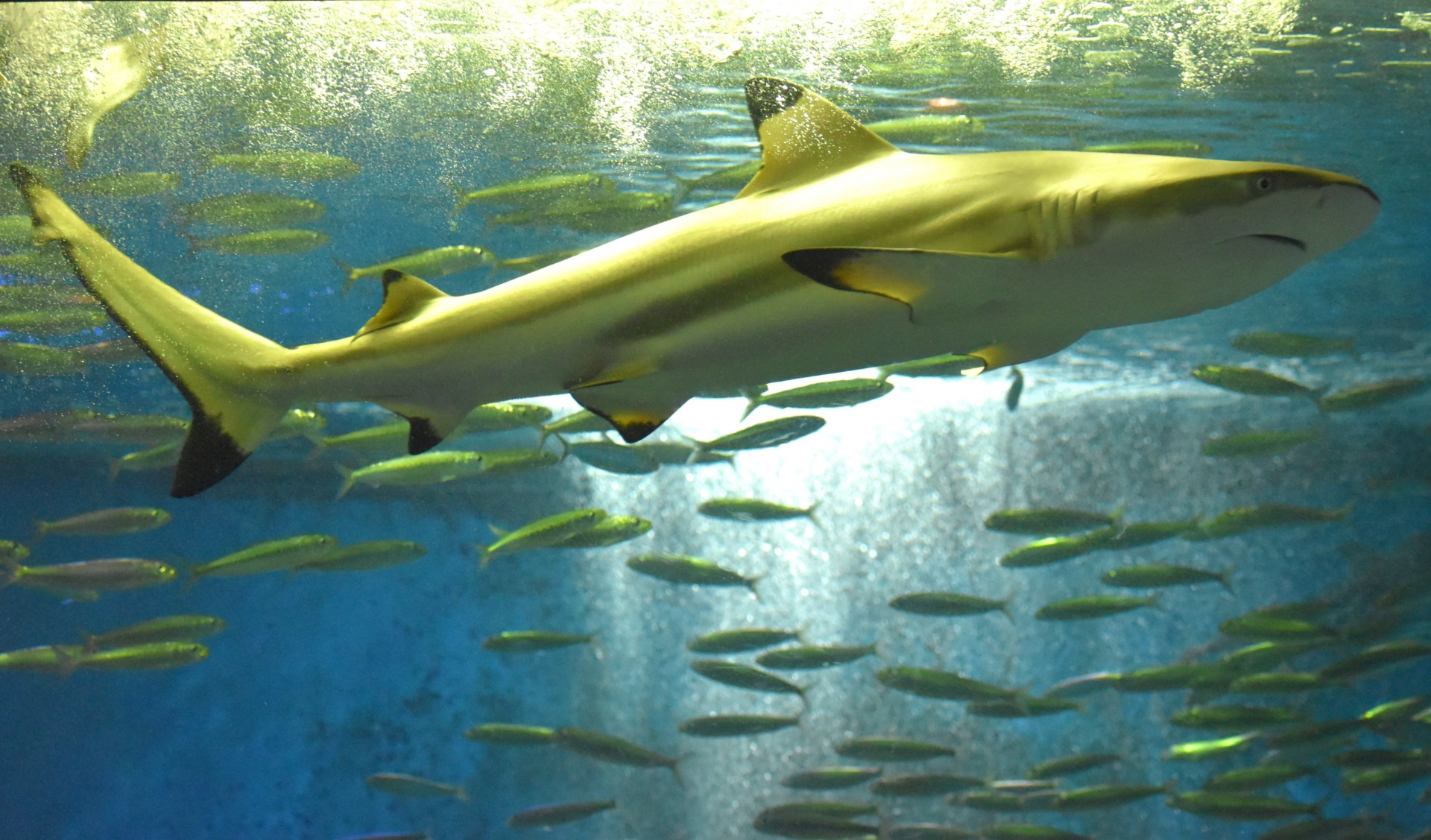しゃぶしゃぶは、美味しい鍋の中でも人気のメニューのひとつです。
みなさんは、当たり前のように「しゃぶしゃぶ」と呼んでいますが、そもそもその言葉の意味は何なのでしょうか。
ここでは、しゃぶしゃぶの名前の始まりや、あの独特な鍋の形や、アク取りをする意味などについてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

腹持ちがいい食材の種類や、効果的な食べ方などについて知りたい
仕事をしている時や、家でテレビを見ている時などに、ついついおやつに手が伸びてしまうことはよくあること...
スポンサーリンク
しゃぶしゃぶの意味と名前の由来についてご紹介
一人で食べても、みんなで食べても美味しい鍋の中でも人気なもののひとつにしゃぶしゃぶがあります。
しゃぶしゃぶは、とっても美味しい鍋ではありますが、その名前の意味や由来、いつから食べられるているのかなどは意外と知られていません。
しゃぶしゃぶの元となった料理は中国で食べられていた「シュワ・ヤン・ロウ」
凍らせた羊の肉を薄く切って鍋に入れる料理から来ています。
シュワ・ヤン・ロウは、戦後の日本に伝わりましたが、その時は羊ではなく、当時よく食べられていた牛肉が使われました。
単純に肉を揺する音が料理名になったわけではなかったのです。
しゃぶしゃぶと言えば、牛肉が主流でしたが、今では豚しゃぶや、鶏しゃぶ、また、本来使われていた羊のお肉、つまりラムしゃぶなども楽しまれています。
しゃぶしゃぶ鍋の独特な形の意味について解説
家ではなく、本格的なしゃぶしゃぶの専門店でしゃぶしゃぶを食べる時に使われるのが、真ん中に煙突のようなもののある、あの独特な形の鍋です。
あれは、一体どのような意味があってあの形をしているのでしょうか。
元々中国で作られた「火鍋子(ホーコーズ)」という名前の鍋
本来の使い方は、真ん中の煙突のようなところの穴から火起こしされた炭を入れて加熱をしていたそうです。
昔はコンロのような便利なものがありませんでしたので、先人の知恵によって作られた形だったのです。
現代では、炭を入れて使用しなくなりましたが、丁度コンロの丸型に合うので、そのまま使われています。
熱の伝導率が良い
鍋の熱が外側と内側から伝わるため、短い時間で加熱することが出来ます。
そしてもう一つが、「外側が熱くなりすぎない」ということもあります。
鍋を楽しんでいる時によくあるのが、鍋の火の熱が外側に流れて、具材を取る手に熱さが伝わってしまうということです。
それが、火鍋子の場合ですと、火の熱気が内側に行きやすくなりますので、火をかけている時に鍋に手を伸ばしても、手が熱い思いをしないで済むようになります。
しゃぶしゃぶの時にする、アク取りに意味はあるのか
しゃぶしゃぶを食べている時に付きものなのがアク取りです。
お肉を食べているとモコモコと出てくるアクは、取るのが当然のように思われていますが、よく考えると、アクを取る意味はあるのでしょうか。
また、そもそもアクとは一体何なのでしょうか。
アクの正体は肉の血などが固まったもの
ですので食べても問題はありません。
料理は見た目が重要
透き通ったダシ汁ではなく、茶色く濁った汁で煮込まれていては、食べる気持ちも下がってしまいます。
また、アクを取る意味のもうひとつは、「ダシ汁を美味しくするため」です。
アクそのものは、お肉や野菜自体の味には影響しません。
ですが、アクがあると、せっかくのダシ汁に雑味が加わってしまい、本来味わうべき味とは異なるものになってしまうのです。
しゃぶしゃぶの具材は、どの順番で入れるのがベストなのか
テレビなどでしゃぶしゃぶを湯がいているシーンを見ると、鍋に野菜が入っていません。
そのため、初めてしゃぶしゃぶを作ろうと考えている人は、いつ野菜を入れて、どんな順番で入れるのがベストなのかがよくわからないと思います。
具材を入れる順は「肉→火の通りづらい野菜→火の通りやすい野菜→肉」
まず最初に肉を湯がいて食べることで、鍋の湯に肉の旨味が溶け込みます。
そうすることで、後から入れる野菜に肉の旨味を入れることが出来るのです。
しゃぶしゃぶのシメにおすすめなものには、何があるのか
しゃぶしゃぶを食べた後のお楽しみと言えば、シメです。
それから、「ラーメン」や、「そば」、「そうめん」のような麺類も安定した人気があります。
少し変わり種のシメの中には、「モチ」があります。
ちょっと意外ですが、ポン酢や胡麻だれとも相性が良いです。
普通の切り餅も良いですが、モチしゃぶ用に薄く切られたモチも売られています。
いつものシメに飽きたという人は、ぜひ一度試してみてください。